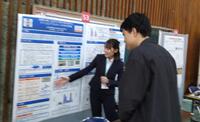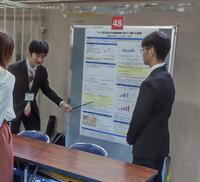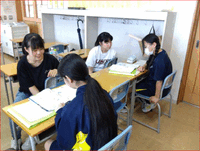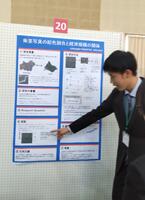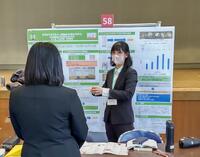News
SSH_北海道大学水産学部見学(SS特講Ⅰ)
2024年7月9日(火)1年生の特講Ⅰ受講者37名が北海道大学水産学部のある函館キャンパスを訪問しました。北海道大学大学院水産科学研究院教授大木淳之先生ならびに教授細川雅史先生の模擬講義を受け、大学の専門的な学習内容に触れることができました。そのあと、研究室訪問や大学生の行っている実験授業の様子を見学させて頂き、真剣に研究に取り組む大学生や大学院生の話を伺い、「大学」で学ぶ楽しさや意義を垣間見ることができました。
【生徒からの感想(一部抜粋)】
○水産学部では海や水生生物を研究していると思っていたけど、生物由来の燃料など化学にもつながっていたり、地球温暖化のことや海水成分の分析など幅広い分野を学べることが印象に残っています。
○大学の構内に入ったのが初めてだったのでとても貴重な体験になりました。
○最初の講義3つは知らないことばかりで、とても興味深くとてもおもしろかったです。
○一番印象に残ったのは、大学生の方々が実験している場面の見学や、水産学部について熱く説明してくれたときです。パンフレットやホームページだけでは伝わらない、リアルな学生像を間近で見ることができて、水産学部、また理系のイメージが深まりました。
○大学の生徒の人達がとても熱心に楽しそうに実験を行っていたのが印象的でした。
本校が訪問した様子は、下記のホームページにも掲載されています。
・北海道大学水産学部HP https://www2.fish.hokudai.ac.jp/infomation/26480/
・北海道大学大学院水産科学研究院地域水産業共創センターHP https://www2.fish.hokudai.ac.jp/rfc/news/20240710.html



夏休み前集会
7月25日(木)に夏休み前集会を実施しました。
3年生にとっては最後の夏休み。
「夏を制する者は受験を制する」を念頭に頑張って欲しいと思います。
また集会後、ALTとの最後のお別れの機会を設けました。
生徒たちはスピーチコンテストやハロウィンなどではお世話になりました。



SS特講Ⅰ_総文祭出場の研究発表から学ぶ
2024年7月24日(水)1年生のSS特講Ⅰ受講生が、この夏、全国高等学校総合文化祭(自然科学部門)に出場する科学部の研究発表を聴きました。研究発表の後には活発な質疑応答が行われ、研究の理解を深めました。これからSS研究基礎の授業で研究活動が始まることから、今回の研究発表の内容は、今後の1年生の研究活動にとって大変参考になるものとなりました。
全国高等学校総合文化祭(自然科学部門)は、8月3日(土)~5日(月)に岐阜県大垣市にある岐阜協立大学を会場として行われます。科学部の研究は「渡島大沼流入河川に含まれる成分の季節変動」をテーマとして、卒業した先輩から研究を引き継ぎ、約4年間かけて集めたデータを用いて分析したものです。
発表の最後には、エールを込めて1年生から大きな拍手を送りました。
☆全国高等学校総合文化祭URL https://gifu-bunkasai2024.pref.gifu.lg.jp/soubunsai/
20240724 SS特講Ⅰ総文祭出場の研究発表から学ぶ.pdf
学習サポートボランティア活動
8月1~2日に本校生徒約 80 名 が、中学生に対しての「学習サポートボランティア」に挑戦しました。
「教わる立場」から「教える立場」へ。
戸惑いながらも貴重な経験を得ることが出来たようです。
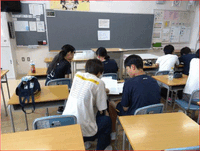
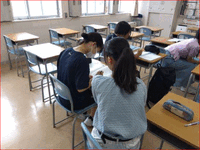
学校説明会終了のご報告
9月7日(土)令和6年度の学校説明会を実施しました。
天気にも恵まれ、多くの中学生・保護者にご参加いただきました。
説明会では、全体会にて吹奏楽の演奏、音楽部中心となった有志による校歌披露、カリキュラム・学校生活・SSH等について説明を行いました。
その後、中学生は2つの模擬授業と部活動説明を受講しました。
たくさんの方にご来校いただきまして誠にありがとうございました。






PTA母の会主催 第1回PTAモルック&親睦会
令和6年10月13日(日) 14:00~ 函館中部高校グランド
晴天の中、40名のPTAの皆さんが集まり、「モルック大会」を開催しました。
多くの皆さんが初モルックでしたが、投げ方やルールの説明をいただき、和やかな雰囲気の中、ゲームに挑戦しました。皆さんの笑顔があふれる中、「ナイスモルック」の掛け声がグランドに響き渡りました。



秋の避難訓練
本日(10月29日)、避難訓練を実施しました。春の避難訓練の反省を活かし、緊張感を持って臨みました。
避難しなければならない状況にならないことが一番良いのですが、万が一に備えて日頃から意識することは重要です。
今回は授業中に生徒一人一人が避難経路を考え速やかに避難できるように意識しての実施でした。



出前講義を実施しました
10月11日(金)4・5校時に、本校1・2年生を対象に出前講義を実施しました。7つの大学から15名の講師の先生にお越しいただき、様々な分野についての講義をしていただきました。
受講した生徒達は、大学での専門的な学びの面白さを体感し、多面的な考えを持つことや論理的に物事を考えることの大切さを学ぶことができました。また、高校での学びが大学での学びの基礎であることを再確認することもでき、大変有意義な機会になりました。
今回の出前講義の経験を今後の学習や進路選択に活かしてほしいと思います。
(ご協力いただいた大学)
公立はこだて未来大学、北海道大学、藤女子大学、小樽商科大学、北海道教育大学函館校
弘前大学、室蘭工業大学



東北大学出前講義(SS特講Ⅰ)
2024年11月1日(金)、東北大学の長尾大輔教授をお招きし、1年SS特講受講者を含む57名を対象に出前講義を行いました。当日は東北大学大学院に通う本校卒業生も来ていただき、長尾教授とともに講義をしていただきました。
生徒たちは東北大学の特色や学校生活、サークルなどの生きた情報に触れ、自分の理想の大学生活についてイメージを持つことができました。また、後半の講義では、化学・工学・バイオテクノロジーを活かしたものづくりについての専門的な学習内容に触れ、化学・バイオ工学科の魅力と「大学」で学ぶ楽しさや意義を感じることができました。
【生徒からの感想(一部抜粋)】
〇実際に東北大学の自分の興味がある学部の話を聞くことができて、より自分のやりたいことを真剣に考えて、勉強に取り組んでいこうと思うことができました。
〇化学・バイオについて、工学部でこのような学びができるんだと思うとワクワクしました。微粒子化による物質の性質の変化についてさらに興味を持ちました。
〇化学・バイオ工学では、私たちの生活をより豊かにするために化学の知識を応用させて日々研究に励んでいることを知り、今私たちが学習しているものは決して無駄なものではなく、自分たちの生活に大きく関わるものであることを実感し、日々の勉強のモチベーションにすることができました。
〇微粒子による技術が多様な形で利用されていること、特にがん治療に関する話や、他分野との関係がわかってとても面白かったです。
〇様々な視点から東北大学についてアプローチして下さり、自分の進路選択がよりイメージできるようになりました。



HAKODATEアカデミックリンクに参加しました
2024年11月10日(日)函館市青年センターにおいて、HAKODATEアカデミックリンクが開催され、本校から特講Ⅱを受講している5グループがポスター発表を行いました。発表を通じて、多くの意見交流を行い、さらに研究を深化させるヒントを頂きました。その中で、「生ゴミの肥料化がもたらす経済効果」の研究をおこなったグループが、ピアレビュー大賞に輝きました。受賞した生徒は、「発表を聞いてくれたたくさんの方と意見交流ができて、本当に楽しかった」と語ってくれました。これからは、2025年1月31日に実施する本校での課題研究発表会に向けて、さらに研究活動を進めていきます。
【発表タイトル】
○生ゴミの肥料化がもたらす経済効果(ピアレビュー大賞)
○衛生写真の配色割合と規模の関係
○ラッパ型玩具の共鳴振動数の変化に関する考察
○渡島近海に生息する魚の消化管内のマイクロプラスチックの存在実態
○昆布からのアルギン酸抽出手順の効率化